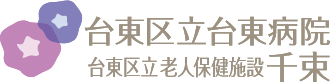老人保健施設千束のご案内
介護のスペシャリストを育てます

大切な利用者のために、そして介護士としての自分のために
老人保健施設千束では介護士の教育に力をいれています。
大切な人に届けたい温かいケアの提供と介護の質の向上をめざして、全介護職員を対象にe-ラーニングを使用した研修とキャリア段位の評価表を使用した介護技術チェックを実施。
介護士による痰の吸引等の研修を実施し資格を習得しています。
外部からの実習も積極的に受け入れ、介護のプロとして自信を持って働ける環境づくりと何より介護を受ける側が満足して頂ける心地よいケアが提供できる人材育成を目標としています。
教育目的
- 介護職としての専門的な知識と技術を習得し、安全で質の高い介護をめざす
- 社会人として責任ある業務ができる介護士を育成する
教育目標
- 介護の専門性を発揮して、チームの一員として役割を果たす事ができる
- 自己流になっている介護技術の改善ができる
- 新人教育には育成計画を立案し、目標を明確にした行動計画をたてる
知識と技術をしっかり習得する事で、 自信をもった介護ケアにつながっていきます。
e-ラーニングを使用した集合教育を実施して介護技術の再確認し、さらに終了後に確認テストをすることで、しっかり振り返りをすることができます。
またキャリア段位の評価表を使用した介護技術の評価を実施。年間計画を立てて各フロアの主任、リーダー格の職員が一般職員の知識、介護技術の評価を行うことで、個々の利用者に適切な介助が日常的にできるように指導しています。

6階:認知専門棟
認知症の症状は一人ひとり違うので、個別ケアが重要です。
老人保健施設千束6階フロアは、認知症状を有するご利用者が入所されている認知症専門棟です。定員は50名。看護師、介護士をはじめ医師、リハビリ、栄養士、相談員等、協力しあうチームケアによりご利用者に寄り添うケアを目指しています。認知症の症状は一人ひとり違うので、個別ケアがより重要になってきます。 認知症の方に大切なことは、自尊心を傷つけないよう接し、その人らしく生活ができるようサポートしていくことです。 むやみやたらにスピーチロックをしないよう心掛けるなど、職員一同、明るい笑顔、元気な挨拶でご利用者と距離を縮めることを大切にしています。
6階の《取り組み》
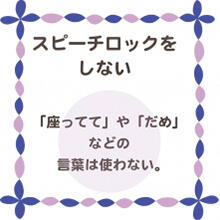
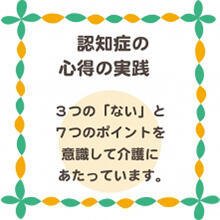
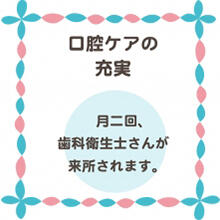
7階:療養棟
地域密着のレクリエーションを考案して、 活動的な毎日から在宅復帰を目指しています。
スカイツリーを望む明るく開放的なフロアが私たちの職場です。ここで医療や機能訓練のスタッフと連携しながら毎日、ご利用者の在宅復帰を目指した支援を行っています。
私たちの施設には長く浅草地域で過ごされてきたご利用者が多く、浅草や隅田川の四季を感じられる行事やレクリエーションを考案し、年間を通じて実施しています。
地域密着の介護を提供することでご利用者にたくさんの思い出を語ってもらい、コミュニケーションを重ねていくことが私たちの大きな喜びです。 ご利用者の笑顔や元気をサポートするためには、介護スタッフのチームワークがとても大切です。 ご利用者の「ずっとこのまちで暮らし続けたい」という気持ちを応援するために、私たち一人ひとりのスタッフがお互いをサポート・協力しながら、ご利用者やご家族から信頼される心のこもった介護を実践しています。
7階の《取り組み》
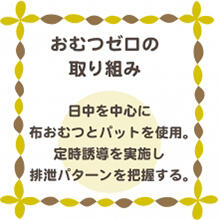
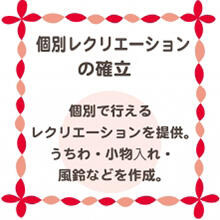
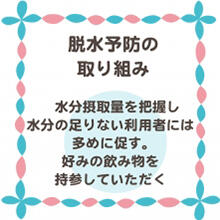
8階:療養棟・医療的処置
医療ニーズへのサポートから在宅へ。 家族と一緒に暮らしを組み立てるスペシャリストが必要です。
8階はベッド数50床、胃ろうや痰の吸引、血糖値管理など比較的医療ニーズの高いご利用者をはじめ身体的な介助を要する方が多く入所されているフロアです。日常生活を通してADLの維持・向上をはかり在宅復帰をめざしています。
浴室は、オンラインバスとチェアインバスの2種類の機械があり、ご利用者の特性に合わせて使用します。他に一般浴もあります。お風呂を楽しみにしているご利用者も多く、満足できる入浴時間を確保できるよう心がけています。
新人指導はプリセプター制でおこない、新人ひとりひとりに指導担当の職員がついて業務をマスターし独り立ちできるようになるまで丁寧に指導しています。
日々のレクリエーションのほか、月ごとの行事を職員が企画し、ご利用者のご家族にも声かけして賑やかにおこないます。家族のふれあいの場として一緒に外出することもあります。
8階の《取り組み》
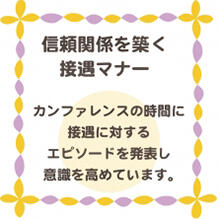
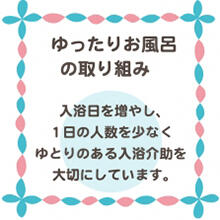
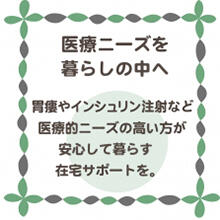
「研修報告」&「先輩のことば」
女川町地域医療センター・支援報告

美しい景色と懐かしさが、僕を迎えてくれました。
海があり、山があり、海産物が美味しいという女川という土地の風景が、私の地元(静岡の東伊豆辺り)にすごく似ている感じがして、知らない土地に来たといういうより、静岡の田舎に帰ってきたという印象で、新しい土地にもすぐに慣れることができました。女川での日々は、とても勉強になり、本当に女川に来れて良かったと感じています。あと勤務は少しですが、最後まで全力で頑張りたいと思います。
仕事について。〜新しい環境で、のびのびと働いています〜
今は、日勤だけの勤務をしています。入浴介助、排泄介助、食事介助と基本的にする事は、老健「千束」と変わりはありません。ただし利用者様が38名くらいのことが多く、仕事には割りと余裕があります。利用者様とゆっくり関わる事ができ、充実した仕事ができていると感じています。 職員の方々も優しい方が多く、わからない事はとても丁寧に教えてくれ、ありがたいです。
唯一、仕事で困った事と言えば、利用者様の方言が強すぎて、ときどき何を言っているか理解できない事くらいです。とはいえ、そんな体験の一つ一つが新鮮であり、毎日のいろいろ学びが、初心の頃の気持ちを思い出させてくれます。
生活について。〜復興の町は、元気を取り戻しつつある印象です〜
東京にいる時との一番の差は、やはり寒暖差です。女川はこの時期、日中でも14℃と東京に比べて寒いですが、寮でエアコン等も使用する事が出来ますし、上着も何枚か準備していったので大丈夫です。住んでいる寮は、何でも揃っており特に不便な所はなく生活できます。寮と施設への行きかえりは車での移動で大体10分程。ただ、復興の為、その辺、道路工事ばかりなので、昨日通った道が今日は通れなかったりとすることもあります。食事に関しては、30分ほど運転して隣の石巻市まで行けばイオンスーパーがあり、女川市内にもコンビニが3件ほどあるので、買い物にも困りません。基本的には不便に感じるところは特になく、新しい環境での生活を楽しんでいます。



小笠原・研修報告

住み慣れた島で安心して、いつまでも暮らしていける環境を。
この度、私は相互派遣という形で、東京都小笠原村にある『有料老人ホーム太陽の郷』へ2か月間の支援に行ってきました。この職場に就職してから7年の間、外部の研修等への参加は経験があるものの、自分の働く施設以外の環境に触れることは今までありませんでした。今回、相互派遣のお話しを頂き、今までの経験や知識がどれだけのものなのか。何が通用して何が足りないのか。改めて今の自分を見つめ直せる良い機会だと感じ立候補させてもらいました。
派遣先の小笠原村立有料老人ホーム太陽の郷は住宅型の有料老人ホームで、島内唯一の高齢者介護入所施設です。居室は10室あり、派遣当時の利用者数は9名でした。 派遣先では、自身の今までの経験や学びを生かし介護技術や認知症患者への対応・心得などを伝えることを目標のひとつとして掲げていました。しかし実際は派遣期間の約2か月間、自らが学ぶ機会のほうが多かったというのが正直なところです。 まずひとつは本来の介護福祉士が担う役割の広さ、大切さを小笠原で再確認したことです。普段の老健千束では昼夜通して看護師が常駐している環境にある一方、太陽の郷においては平日のみ日中看護師が1名、夜間は併設の診療所看護師が兼任の形で1名という環境です。そのため、常に看護師が居る環境ではありません。そういった点から配薬や点眼、バイタルサインの測定などは基本的に介護士が行っていました。利用者の飲んでいる薬の内容や時間、注意事項、ひとりひとりのバイタルの平常値など、より細かく把握しておく必要がありました。老健千束においてもそういった点はもちろん求められますが、やはり看護師が常にいる環境下でありどこか安心してしまい、意識が薄らいでしまったのだと自身で振り返りました。こうしたことを踏まえ、改めて介護福祉士として看護の要素も最低限学んでおく必要があることを再認識しました。
さらに島内には手術を行える設備がないため、必要となった際は提携している病院への搬送となります。即ち内地(本土)への搬送となり島を離れざるを得ません。手術を終え無事に帰島出来れば良いですが、環境の変化による心身への影響が大きいことは言うまでもなく、高齢者にとってはより大きな負担となる訳です。太陽の郷において「住み慣れた島で安心して生活でき、いつまでも暮らしていける環境を提供する」ということも、島唯一の施設として大事な要素となってきます。小笠原にはアメリカの統治下にあった時代があり、入所されている方々はそんな大変な時代を生き抜いてきました。統治下の時代を経て、現在は生まれ育った小笠原で暮らせています。慣れ親しんだ島でいつまでも暮らしていけるよう、利用者に対して介護士はできる限りのケアを施す必要があります。
日頃のリスクマネジメントや細かな点への気づきはとても意識が高く、島で暮らし続けられるよう使命感を持ってケアに努める姿勢を見て、同じ介護福祉士として大きな刺激を受けました。
「先輩のことば」
〜私の仕事・私の思い〜「現実は想像力をかきたてる」
「“ ずっとこのまちで暮らし続けたい ” を応援します」の理念のもと、当施設は、地域との連携、在宅復帰や看取りを積極的に行っています。
また、病院が階下に併設されているので、他施設では受け入れが難しいような医療行為が必要な方も入所されています。「危険の芽を摘むことはできないか。事故になるずっと前に気づけたら」と、平成29年度から職員一人ひとりの気づく力(想像力)を伸ばすことを目的に、「気づいたぞう」を始めました。
「気づいたぞう」とは、普段の業務で「気になったこと・気づいたこと」を、他の人たちにも知ってもらおうという取り組みです。「気になったこと・気づいたこと」ならなんでもOK。すぐに事故に結びつかないと思われることでも報告してもらいます。みんなの「気づき」から想像し、どのようなことが 起こり得るかを考えることで、いつかどこかで、事故を未然に防げるかもしれない。そういった、職員の気づく力(想像力)を伸ばすことができたらと考えています。
気づくとは、「一歩先のこと」を想像する力です。気づいたことで、少し先の未来を想像し準備ができます。準備することで、心や時間に余裕が生まれます。余裕が生まれれば、まわりの人や環境が見えるようになります。現場にはさまざまな危険が潜んでいます。よく見て感じることで、未来への想像力も豊かになります。この取り組みを続けていき、誰にとってもよいと思える施設をめざしたいと思います。